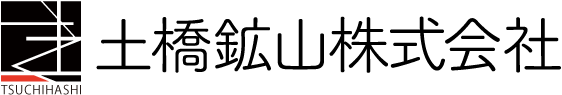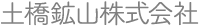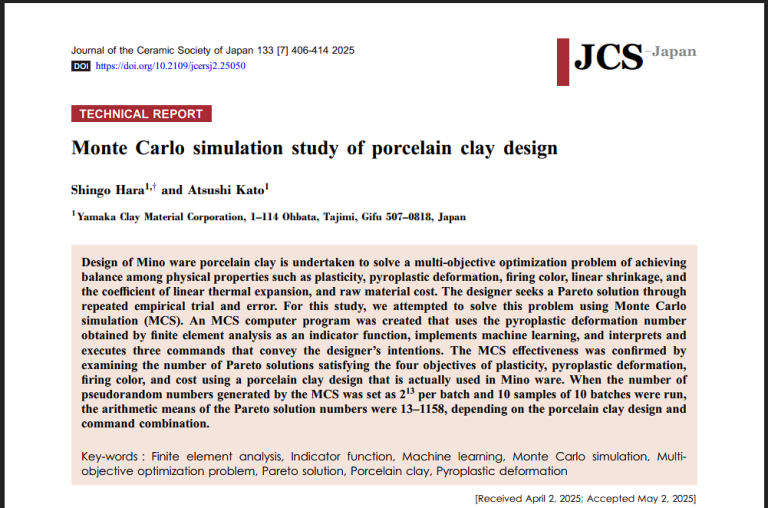鉱山ブログ
お盆に入りました。
弊社は、8/9(土)~8/11(月)の3日間と、8/14(木)~8/17(日)の4日間がお休みとなります。8/12(火)、8/13(水)は通常通り営業となります。
本日は8/11(月)ということでお休みですが、電話もかかってこないし、地下の現場から呼び出しを受けることもないので、のんびりと事務所でパソコンに向かっています。
ここ最近、AI(人工知能)がとても話題になっていますね。ちょっとした事務作業やレポートであれば、もうAIがやってくれるみたいですが、弊社のようなクラシカルな業界では、AIなんてなんの関係もないものと思っていました。
ところが、そうでもないようです。
このところ、陶磁器原料を作る方法や鉱山開発において、AIを活用する新たな事例について、研究者の方からお伺いする機会がありました。AIをうまく使えば、かなりの省力化や効率化が期待できるみたいです。
1つ目は、弊社のお客様である岐阜県多治見市のヤマカ陶料様に勤めていらっしゃる原真吾さんたちが発表した論文です。
日本セラミックス協会論文誌「JCS-Japan」に掲載されたもので、以下のURLから閲覧できます。
https://doi.org/10.2109/jcersj2.25050
英語で書かれてますので一瞬ひるみますが、AIを使って翻訳と概略をまとめてもらって、おおまかな内容を読むことができました。
こちらの論文は、美濃焼を作るための原料つまり坏土の調合について、AIを使って調合比率などを決めるために、モンテカルロ法という手法を使う、というものです。(だと思います。自信ないです)
AIや大容量の計算機を使うことで、大量のシミュレーションが短期間で可能になり、最適な調合レシピができるわけです。坏土には国内から海外までさまざまなクセのある天然の粘土や陶石を使うことから、配合比率を決めるのは、長年の経験で培われた熟練の技だったわけですが、今では人手不足や景気の低迷によって、熟練の技がうまく伝承できなくなる可能性が出てきました。
そこで、このモンテカルロシミュレーションを使うことで、最適な調合レシピを短時間で導き出すことができる、ということになります。
陶磁器の世界はオールドセラミックスと呼ばれて、どちらかといえば古い産業のイメージがありますが、こうしたAIの活用で、まだまだ新しい技術革新が起こせるかもしれない、といった感じがしました。
もう1つが、長崎の窯業試験場におられた研究者の方から教えていただいた、坑内採掘に関する新技術の研究発表です。
先日開催された資源地質学会の講演会にて、北海道大宅の研究グループが発表された「VNIR法」というもので、地下坑道の切羽を写真に撮り、その写真をAIに分析させることで、軟質岩と粘土の部分を色分けして表示するという技術です。多分そんな感じです。
こちらの講演会のプログラムにある「南薩型金鉱床におけるハイパースペクトル画像とAIを用いた酸性変質帯の判別」という発表です。
弊社地下坑内の切羽は、セリサイト、パイロフィライト、モンモリロライト、カオリナイト、ダイアスポあ、珪石(シリカ)などが複雑に入り混じった形で出てくることが多く、特にセリサイトからパイロフィライトに変化する際に、中にモンモリロライトなどが多くかんできて、陶磁器原料としての品質を大きく変わってくる可能性があります。
切羽を注意深く観察して採掘しているつもりですが、はっきり言ってベテランでも見た目でわからないことが多く、なかなか苦労しているところです。
もしも、こちらの研究を活かした分析装置があって、写真をパチリと一枚撮るだけで、セリサイトやパイロフィライト、モンモリロライトの付帯状況がわかるならば大変便利だと思います。
私はパソコンが大好きで、この30年間ずっとパソコンを触ってきましたが、正直なところ、今のAIとかよくわかっておらず、ついていけてない状態です。とはいえ、あゆみを止めるわけにはいかないみたいです。
この2つの論文をご紹介いただいた方は、いずれの方も私よりもご年配なのですが、こんな難しいAIの世界を理解しながら日々研究を続けておられます。私ももうひと頑張りしなきゃならんですね。がんばります。